退職はしないが仕事に意欲を見せず最低限の働きしかしない「静かな退職」は、チームの士気を下げるなどの問題があります。どのような対策が有効かを考察します。
はじめに
近年、「静かな退職」という言葉が広がっています。これは辞表を出すわけではなく、与えられた業務だけを淡々とこなし、それ以上の創意や努力を避ける働き方を指します。従業員本人にとっては燃え尽きを防ぐための自衛的な行動かもしれません。しかし、企業にとっては業務改善や新しい提案が生まれにくくなり、将来的な競争力を削ぐ恐れがあります。
以下、中小企業において静かな退職を防ぐために実行できる具体策を考察します。
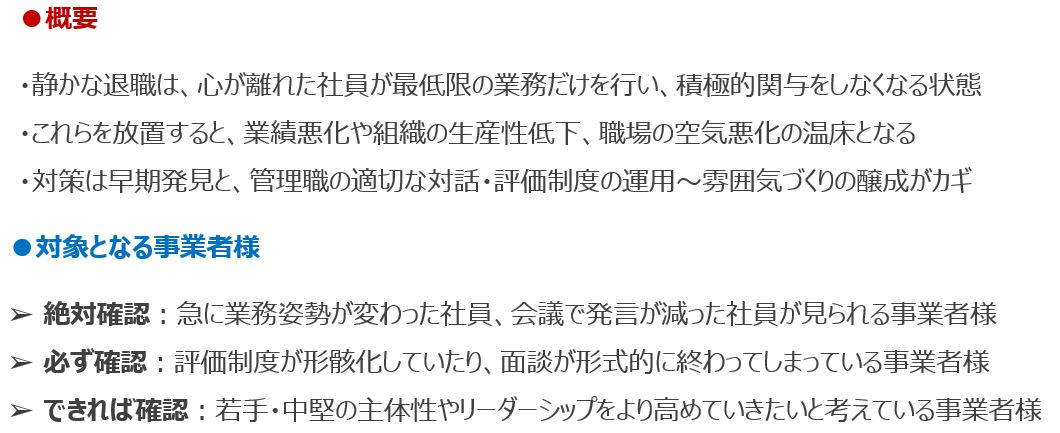
なぜ静かな退職が起きるのか?
「静かな退職」の原因として以下のものが考えられます。
-
評価・給与の「頭打ち感」
「頑張ってもどうせ評価されない」「もう昇進はできなさそうだ」「この先たいして給料が変わらない」という状況が続くと、やがて「もう会社や自分に期待しない」という諦めに変わります。
-
過度な期待と業務の偏り
人手不足の現場では、ベテランや真面目な社員に仕事が集中しがちです。「また自分ばかり」「どうせ誰も助けてくれない」「自分は貧乏くじばかりだ」という気持ちが蓄積すると、自然と仕事への熱量は下がっていきます。
-
未来が見えないことへの失望
「この先、この会社で何ができるのか分からない」「成長のチャンスがない」「仕事内容に意義を見出せない」「普段の生活に楽しみがない」といった、仕事やプライベートにおける漠然とした将来不安は、特に若手や中堅層に強く影響します。「大した未来じゃない」と本人が諦めた瞬間、静かな退職が始まります。
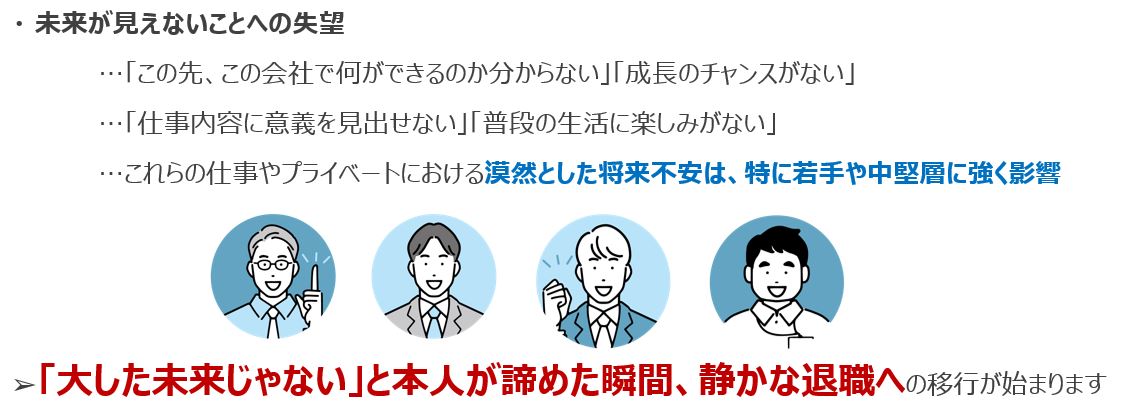
「静かな退職」は問題なのか?
一見すると、最低限の仕事をこなすため「静かな退職」は大きな問題ではないようにも見えます。しかし静かな退職者は、従業員間の前向きなコミュニケーションに非協力的になりがちです。
その結果、社内で創意工夫や改善提案がなされず、組織の成長性を損なうことになるでしょう。また一方で、静かな退職は賃金の公平性を損なうリスクがあります。無気力な先輩の給与がやる気のある若手より高いといった不公平は、意欲的な人材の離職につながる点で問題となり得るでしょう。
実践的な対策
静かな退職を未然に防ぐには、職業生活に継続的な「刺激を組み込む」以下のようなアプローチが検討できます。
-
対話のスケジュール化(会話による刺激)
「ベテランと新人」、「同期同士」または「他部署の従業員同士」などの小グループでのカジュアルな対話を業務スケジュールに組み込む方法です。愚痴大会にならないように改善提案や褒め合うルールなどポジティブなテーマを設定しても良いでしょう。
-
新規プロジェクト立ち上げ(仕事の変化による刺激)
同じ仕事のマンネリによるモチベーション低下を防ぐために定期的に新規プロジェクトを立ち上げ、本人同意の上で任せる方法です。未来に向けた活動に従業員を巻き込むことで後ろ向きの姿勢の抑制が期待できます。
-
評価基準の見直し(報酬による刺激)
それぞれの仕事の意義や目的、求められる結果と報酬の関係を明確にした評価基準を策定することも効果が期待できます。成果に応じて賞与や手当の変動幅を設けるなど、法的に適切な範囲で給与に反映する制度を作ってはいかがでしょうか。
