2024年2月に厚生労働省は飲酒に伴うリスクに関する知識普及のためのガイドラインを公表しました。労務管理上関係が出てくる部分について解説します。
はじめに
2024年2月、厚生労働省から飲酒に伴うリスクに関する知識普及のため、適切な飲酒量・飲酒行動の判断に資する「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」が公表されました。
労務管理上、業務に関連した飲酒についてこのガイドラインを参考として様々な判断を行う場面が出てくると予想されます。以下、労務管理上関係がありそうな部分について解説します。
ガイドラインの概要
今回の「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」の概要は以下のようになっています。
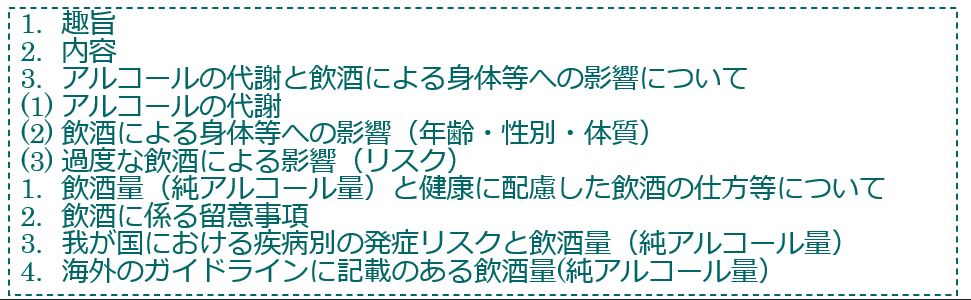
労務管理に影響する部分
-
20歳代の社員の飲酒
このガイドラインの中に、年齢の違いによる影響について述べている箇所があります。「10 歳代はもちろん20 歳代の若年者についても、脳の発達の途中であり、多量飲酒によって脳の機能が落ちるとのデータがあるほか、健康問題(高血圧等)のリスクが高まる可能性もあります」とあり、20歳代の若年者が業務に関連した酒席において飲みすぎないように注意するほか、20歳代の社員に対して飲酒の強要をすることがないように注意しましょう。
ポイント:20歳代以下の社員の飲酒量に注意する
-
過度な飲酒による影響
「過度な飲酒による影響」の中に「急激に多量のアルコールを摂取すると急性アルコール中毒になる可能性があります」と説明されています。また、「避けるべき飲酒等」として「一時多量飲酒(特に短時間の多量飲酒)」「他人への飲酒の強要等」が挙げられています。会社の懇親会でのイッキ飲みの強要や飲み放題で各自のペースを考えずにお酒をどんどんオーダーするなどの行為は労務管理上問題となる可能性があります。
ポイント:イッキ飲みNG、飲み過ぎも注意
-
飲酒量の把握の仕方
ガイドラインに示されている「我が国における疾病別の発症リスクと飲酒量」表によると、男性の場合1日40g以上の飲酒により脳梗塞の発症リスクにつながり、また1日60g以上の飲酒により肝がんの発症リスクにつながるとされています。もちろん人体への影響は体質差がありますが、この飲酒「量」についても以下の計算式を参考にしてはいかがでしょうか。
ポイント:お酒に含まれる純アルコール量の算出式
摂取量(ml) × アルコール濃度(度数/100)
× 0.8(アルコールの比重)
例: ビール500ml(5%)の場合の純アルコール量
500(ml) × 0.05 × 0.8 = 20(g)
