2024年元旦の能登半島沖の震災によって、改めて日本における災害対策の重要さを思い知らされることとなりました。緊急時の企業活動を支えるBCPについて解説します。
はじめに
2024年元旦に起こった能登半島沖の震災により多くの方が被災し、現在も復旧に向けた各種支援が続いています。地震の多い日本において、天災地変の際に企業活動をどのように復旧・維持していくかの計画を立てておくことの重要さを今回改めて思い知らされることとなりました。以下緊急時に有効なBCPについて解説します。
BCPとは
BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。BCPは2001年のアメリカ同時多発テロを契機として注目されるようになりました。
実効性の高いBCPを策定することで、顧客からの信用アップに寄与するだけでなく、公的な認定を受けることで税制優遇や融資上の優遇などのメリットにも繋がります。緊急時に慌てて対応せずに済むように、災害を具体的に想定し、災害毎の対策や命令系統、安否確認などを体系的に計画することは、企業価値の維持・向上にもつながるでしょう。
BCPの内容
BCPは主に次のような項目で構成されます。
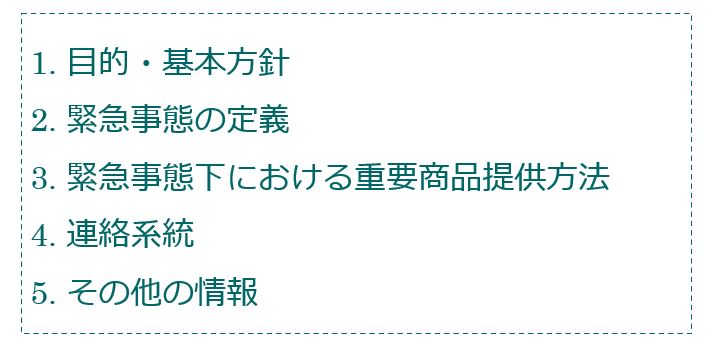
【1. 目的・基本方針 】
「緊急時において関係者の安全を確保しながら事業活動を継続するため」「従業員の安全を第一に考える」「顧客の緊急事態下における事業活動を支援する」など、計画が何のためにあるかを記述します。
【2. 緊急事態の定義】
「震度6以上の地震」「大規模火災」などといった天災地変の定義、またそれらの災害に付随して「水道とガスが停止した状態」「通信インフラが使えない状態」「物流インフラが使えない状態」など、どんな場面をBCPの対象とするかを定義します。
【3. 緊急事態下における重要商品提供方法】
什器や設備、通信機器の保全や代替設備の確保、データバックアップを復旧するためのワークフロー、緊急事態下における従業員の労働環境確保、協力企業との連携などについて定めます。
ポイントとしては①不足するリソース(人・モノ・金・情報等)を補完・代替する方法について定めること、②「誰が、何を、いつ」行うかについて具体的に取り決めることでしょう。
【4. 連絡系統、権限】
安否確認の時期と方法、統括責任者や統括代理者の明示、災害対策本部の設置基準、設置の場所候補地などについて策定します。安否確認については通常の電話・インターネット通信網が使えない可能性もありますので、代替的なサービスの導入を検討しても良いでしょう。
【5. その他の情報】
緊急時に役立つハザードマップや地域の避難場所、警察や消防署など緊急連絡先の情報を盛り込んでも良いでしょう。
